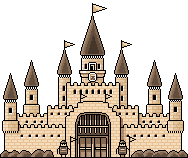<筑波山>
日本百名山のひとつにも挙げられる筑波山は、坂東無双の霊山。
「西の富士、東の筑波」と並び称されるほど。
関東平野の北東に、すっくと立つ優雅な山容は古来より
高貴な色、紫で表され「紫の山」「紫峰」と呼ばれます。
神々の山として万葉の歌人が様々な歌に詠んだことでも有名です。
山は二つの峰からなり、南から向かって右が女体山877m、左側が男体山871m。
神代の昔、イザナギ、イザナミの二柱の神様が山頂の「天浮橋」に立ち、
手にした鉾の先から滴を垂らすと、それが日本の国になったと古事記に記されています。
<筑波山神社>
約3,000年の歴史を有する筑波山神社。
関東の霊峰・筑波山を御神体としています。
波筑波峰に筑波山女大神(イザナミノミコト)を祀ります。
神武天皇元年には、両山頂にご本殿が建立されたといわれる古代山岳信仰の形を
今にとどめる関東屈指の名社です。

※スーツ姿&革靴での登山は危険です・・・
|

筑波山神社(随神門) |
拝殿前に建てられている随神門は、
間口5間2尺、奥行3間の楼門で、
茨城県内では随一の規模。
古くは寛永10年(1633年)に
3代将軍徳川家光により寄進されたが、
宝暦4年(1754年)に焼失、
再建されるも明和4年(1767年)に再度焼失した。
現在の楼門は、その後の
1811年の再建によるものである。
|

筑波山神社(拝殿) |
筑波山神社は筑波山中腹にある、
全国屈指の由緒ある神社。
拝殿前の茅の輪をくぐることにより、
身についた穢れを祓い、
疫病などを防ぐとされています。
  |

春日神社(本殿)・日枝神社(本殿) |
筑波山神社拝殿の奥、
向かって右に日枝、左に春日の社が建つ。
日枝神社の三猿は、
日光東照宮のものより早く造られた。
春日神社本殿・日神社本殿は三間社流造、
1633年、3代将軍徳川家光公の寄進で造られた。
|

御神橋 |
切妻造柿葺屋根付。間口1間、奥行4間。
通常は渡れない。
春と秋の御座替祭(4月1日、11月1日)、
年越祭(2月10・11日)のときのみ
参拝者は渡ることが出来る。
1633年11月、3代将軍徳川家光公の寄進で
造られ、1702年6月、5代将軍徳川綱吉公
によって改修されている。
安土桃山時代の様式をなす荘厳な造り。 |

厳島神社 |
江戸時代初期、1633(寛永10)年、
3代将軍徳川家光公の寄進で造られた。
琵琶湖の竹生島神社の御分霊を祀る。
祭神は市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)。
琵琶湖と同じイメージにするため、
周囲を池で囲まれている。 |

筑波山神社(男体山本殿) |
標高871m!御幸ヶ原から約15分
徳川幕府の守護山としてもあがめられていた
筑波山の男体山御本殿は、
江戸城の方向を向いています。
  |

筑波山神社(女体山本殿) |
標高877m!御幸ヶ原から約15分
山頂にある女体山の御本殿は,
男体山御本殿の方を向いています。
  |

天浮橋 |
日本神話によると、
天上界と地上をつなぐ橋で、
イザナギ、イザナミの両神が降臨したところ。
 |

ガマ石 |
御幸ヶ原から女体山を目指して歩くと
カエルのような石が…。
筑波山の奇岩・怪石の中でも有名な
「ガマ石」です。
口の中に石を投げいれると
お金持ちになれると言われています。
|